柿は古くから日本人にとって重要な果樹である。およそ「甘味」といったものが現在と比べて極端に少なかった時代み、柿の甘味は貴重であった。
食べ方、材の利用、薬理から、民族学的視点も交えて、知見を共有する意味がある。
季節柄、柿を話題にしようと思います。
「わが国独特の果樹で、雌雄同株。若葉は柿茶や天ぷらに、へたはしゃっくり止めに、柿渋は血圧降下に、すべてが健康づくりに役立つ。」
これは【伊沢一男:薬草カラー図鑑】の「かき」対する紹介文で、ここまで力強く、健康への有用な影響を述べているのは、珍しいです。
もちろん、健康に対する評価よりも、とにかく私は「かき」が大好物なのです。数年前に、女房の友達の筋から、段ボール1箱分の次郎柿をいただいたことがあり、およそひと月のあいだ、比較するものが思い浮かばないぐらいの幸福感を、味わい続けたことがあります。
ただ、それ以来、そういったことは二度とありません。毎年、秋になると、女房相手に「かき」の便りはないものかと、あからさまな催促を繰り返しているのですが。
「かき」は、この果実の部分の名称であって、植物全体としては「かきのき」が正式な名称です。
日本の古い時代の記録や化石から、「かき」につながるものが見つかっていないことから、奈良時代以降に中国からつたわったものらしいといわれています。
それ以降、日本でさまざまな品種に改良され、現在では東南アジア中心に栽培されています。

1.主な品種について
(完全甘柿)
・富裕・・・最多栽培
・次郎・・・富裕同様、日持ちで劣る
(不完全甘柿)
・西村早生・・・種子が少ないと渋み残る
・ふで柿・・・極早生
(完全渋柿)
・平核無(ヒラタネナシ)
・四溝(ヨツミゾ)
・堂上蜂屋・・・干し柿専用
(不完全渋柿)
・甲州百目・・・熟すと渋みが抜ける
不完全甘柿は、種子ができると、その周辺に「ごま」というタンニンが凝固したものができ、果肉が甘くなるものをいいます。タンニンが凝固する前の状態だと「渋柿」です。
不完全渋柿は、種子のまわりの「ごま」ができた部分のみが甘くなり、そのほかは渋いままのものをいいます。
以上は、【朝日百科:植物の世界№62】からの引用ですが、文中では「平核無」を渋抜きして食べることを、『強く』勧めています。
おそらく、生涯一度も食べたことがありませんし、手に入れたからといって、いきなり渋抜きがうまくできるかどうかわかりません。それにしても、一度は口にしてみたいと、『強く』思いました。
ついでに、同文中より、渋抜きについても引用します。脱渋(渋抜き)とは、タンニンを唾液に溶けない物質に変えることです。
・湯抜き・・・50~60℃に沸かした湯につけて翌日まで放置し、それを3回繰り返す。
・アルコール脱渋・・・35~40%のエチルアルコールを噴霧して、1週間密閉する。
・炭酸ガス脱渋・・・ポリエチレンの袋にドライアイスと一緒に4日ほど密閉する。
湯抜きは江戸時代から行われている方法で、私がやるとしたら、おそらくこれだなと、直感しました。

2.木材部分の利用
一番よく知られているのは、英語表記の「persimmon」でわかるように、ゴルフのウッドクラブのヘッドに使われています。つまり、十分に乾燥した材は「硬い」ということです。同様な理由で、かつては囲炉裏の炉端を囲む材として使われています。
近縁種の「コクタン」も耐久性の高い材として、利用価値の高いものです。床柱、仏壇などが有名なところです。

3.薬理について
【南江堂:生薬学】
使う部分は、いわゆる「ヘタ」の部分で、これを「柿帯(シテイ)」と呼んでいます。日本薬局方の局外とされています。「ヘタ」に含まれる成分が胃中で凝固し、『物理的に』しゃっくりを止める、とあります。
なんか、すごいですね。
【伊沢一男:薬草カラー図鑑】
柿渋(渋味の強い青柿のヘタを取り、すり鉢などの容器で水を加えながら砕く。5~6日したら布でこして、汁をびんに入れ、半年ほど土中に埋めておく)を服用する。また、乾燥した葉を煎じて飲むと、血圧降下の作用がある。
過去記事:血圧対策を変更します!よさそうと思っていた「カゴメトマトジュース」に効果なし!
でも書きましたが、自分はいささか血圧に問題があるようなので、「柿渋」はためしてみる価値がおおいにあると感じます。
日頃、血圧対策のためのサプリ探しなどと思っていましたが、もともと十分に知見があると自負していた分野でも、忘れていたり、見落としているものが、まだまだあることを知らされました。
4.民俗学的知見(Folklore)
【柳田国男監修:民俗学辞典】に、「かき」についての興味深い記述がありますので、それを知っていただきたいと思います。
果樹の代表的なものとして親しまれ、したがってこれに付随する禁忌俗信も多い。木まぶり[果物]や成木責の呪法も、主として柿の木に対しておこなわれる。柿の木は折れやすいものであるが、柿の木から落ちて怪我をすると一生治らないとか、馬鹿になるとか死ぬとかいう。また柿の木を火葬の燃料に使うところがあり、常の日は囲炉裏にくべることを忌んでいる。・・・中略
柿の貯蔵法には単に干して甘くしたり、樽につめて渋を抜いたり、塩漬けにする方法などがある。・・・
ちなみに、「木まぶり」とは、果物を一つだけ獲らずに残しておくことで、いわゆる「木守柿」のことです。
また「成木責」とは、刃物で樹皮に傷をつけ、「なるかならぬか、ならねば伐るぞ」「なります、なります」といった問答をおこない、その年の豊穣を約束させる呪術です。梨や桃の木に対してすることもありましたが、柿の木に対しておこなうのが普通であったといわれています。
こうしてみると、「かき」は私たち日本人の実生活や風習の面でも、古くから大きなかかわりを持った植物であるということがわかります。
私の住む地方でも、郊外の農業地帯に行けば、たいがいの農家の庭先には立派な柿の木が植わっており、秋になると実にたくさんの実をつけているのが見られます。
そういった場所を通るたびに、「いったいあれほどの量の柿を、だれが食うんだろう」と、いつも余計な心配をしてしまうのです。


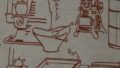
コメント